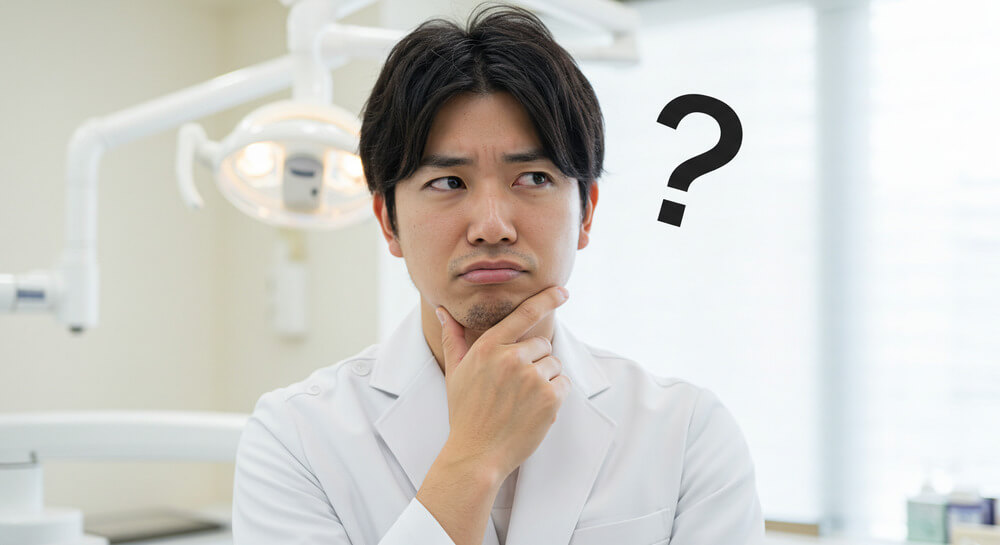「先日、厚生局から個別指導の通知が届いた…」「最近、同業者の間で個別指導が厳しくなったと聞くけど、うちの医院は大丈夫だろうか…」
歯科医院を運営される院長先生や事務長の方々にとって、厚生局による歯科医院の個別指導は大きな不安要素の一つではないでしょうか。
この記事では、歯科医院の個別指導とは何か、どのような場合に指導対象となるのか、そして実際に通知が来た場合にどのように準備し、対応すればよいのかを、網羅的かつ分かりやすく解説します。
個別指導の目的や流れ、指摘されやすいポイント、そして万が一の事態を避けるための日常的な対策まで、この記事を読めば、歯科医院の個別指導に対する不安を軽減し、適切な準備を進めるための一助となるはずです。
歯科医院に対する指導とは

歯科医院に対する指導とは、厚生局が歯科医院に対して、保険診療のルールを周知徹底し、適切な診療・請求が行われているかを確認するために行う指導のことです。しかし、一口に「指導」と言っても、その種類はいくつかあり、それぞれ目的や対象が異なります。今回は、歯科医院が知っておくべき主要な4つの指導形態、すなわち集団指導、集団的個別指導、新規指導、個別指導について、その内容と対策を詳しく解説します。
集団指導
新しく保険医療機関として指定されてから約1年以内の歯科医院や、診療報酬のルールが変更される際などに実施される説明会のようなものです。
保険診療の基本的なルールや、診療費の請求事務について分かりやすく説明されます。参加は推奨されますが、もし都合が悪く欠席しても、特に罰則はありません。
集団的個別指導
前年に提出されたレセプト(診療報酬明細書)1件あたりの平均点数が、その都道府県の平均点数の1.2倍を超え、かつ高額な上位約8%に入る歯科医院が対象となる指導です。
講義形式の集団部分と、少数のレセプトに基づいて個別に話をする部分で構成されますが、最近では集団での説明がほとんどを占めるでしょう。もし正当な理由なくこの指導への参加を拒否すると、後述の「個別指導」の対象になる可能性があります。
参照:厚生労働省「集団的個別指導及び個別指導の選定の概要について」
新規指導
新しく開業した歯科医院が、保険医療機関としての指定を受けてから約6ヶ月から1年以内に受ける指導です。これは主に教育的な意味合いが強いとされていますが、もしこの指導の場で、不正や著しい不当な診療・請求が確認された場合、監査に移行することもあり得ます。
最悪の場合、保険医療機関の指定や保険医の登録が取り消されてしまうケースも存在します。歯科医院の9割以上が新規指導の対象となるため、開業したばかりの先生方は特に、この指導を軽視せず準備を進めることが大切です。
個別指導(都道府県個別指導)
これまでの集団指導とは異なり、この個別指導は、患者さんや元職員からの情報提供があった場合や、過去の指導で改善が見られなかった場合、あるいは監査で注意を受けた場合などに実施されます。
また、集団的個別指導の結果、不適切な点が認められた場合にも対象となることがあります。この個別指導を正当な理由なく拒否すると、さらに厳しい「監査」の対象へと進む可能性が出てきます。
個別指導の流れと対応のポイント

歯科医院への個別指導は、実施の通知から始まり、指導当日、そして指導後の結果通知と改善報告という段階を経て進行します。各段階で適切な準備と対応を心がけることが、円滑な進行のために非常に重要となります。
実施通知の受け取りから指導日までの準備
個別指導の始まりは、地方厚生局から送られてくる「指導実施通知書」の受け取りです。この通知は通常、個別指導日の約1ヶ月前に届きます。通知を受け取ったら、速やかに指導に向けた準備に取り掛かることが求められます。
具体的には、まず指導日の1週間前には、指導対象となる患者さん20名分の氏名がFAXで伝えられます。さらに、指導日の前日正午には追加で10名分の患者さん氏名が通知される運びです。
これらの患者さんの診療録や関連書類を迅速に準備し、指導当日に質問された際にすぐに提示できるよう、きちんと整理しておく必要があるでしょう。この準備期間中に、もし不安な点があれば、弁護士など専門家への相談を検討することも賢明な選択肢です。
指導日当日
個別指導は、通知に記載された指定の日時に、一般的には地方厚生局の会議室で実施されます。指導の場には、地方厚生局や都道府県の職員が複数名参加し、さらに歯科医師会から派遣された立会歯科医師も同席します。
指導の主な内容は、事前に選定された患者さんの診療報酬明細書に基づき、おおよそ6ヶ月前の連続する2ヶ月間の診療について、口頭での質疑応答形式、すなわち面接懇談方式で進められます。指導時間は通常2時間を予定しているようです。
もし指示された書類が不足していたり、対象患者さんの保険診療内容について十分な説明や回答ができなかったり、あるいは診療内容や請求に不正や不当の疑義が生じた場合には、指導が中断され、後日改めて再開されることがあります。
また、明らかに不正または著しい不当が疑われる事態が発生した場合は、個別指導が途中で中止され、さらに詳細な調査を伴う「監査」へと移行する可能性も十分にあります。この指導の場には、弁護士は委任状を提出すれば同席することができますが、歯科医師の代理として質問に回答することは認められていません。
指導内容を後で確認するためであれば、録音の許可を求めることも可能です。なお、厚生局には診療録のコピーを求める権限はなく、歯科医院側もこれに応じる義務はないという点も理解しておくべきでしょう。
指導日以降の対応
個別指導が終了した後も、いくつかの手続きが継続されます。まず、個別指導の結果と、それに応じた指導後の措置について、原則として指導日から1ヶ月以内、遅くとも概ね2ヶ月以内には、地方厚生局から文書で正式に通知が届きます。
この通知を受け取った歯科医院は、その内容に基づき、1ヶ月以内に「改善報告書」を作成し、提出しなければなりません。
さらに、指導対象となったレセプトの中で返還が必要と判断されたもの、そしてその返還事項に関連する全患者さんの過去1年間のレセプトについて、歯科医院自身で自主的に点検を行い、もし過誤が認められた場合は、その差額を返還する手続きを進めることになります。
個別指導の結果の分類

個別指導の結果は、概ね妥当、経過観察、再指導、要監査の主に4つの区分で通知されますが、それぞれの結果が持つ意味合いは大きく異なります。
| 指導結果 | 意味合い | 主な影響と対応 |
|---|---|---|
| 概ね妥当 | 問題なし(指摘は軽微) | 良好な結果。追加措置は基本的に不要。 |
| 経過観察 | 一部改善が必要 | 改善報告書提出。改善が見られないと再指導の可能性。 |
| 再指導 | 複数または重大な問題あり | 改善報告書提出。翌年度も個別指導対象の可能性大。 |
| 要監査 | 不正行為の疑い | 指導中止、直ちに監査へ移行。重い処分につながる。 |
また。この結果は以下の4つの重要な観点から総合的に判断されます。
・診療が医学的に適切だったか
・保険診療のルールを守っていたか
・診療録が正しく記録されていたか
・保険診療や請求の知識が十分だったか
それぞれの結果分類について詳しく見ていきましょう。
概ね妥当
この結果は、指導中に指摘された事項や返還が必要な金額がごくわずかで、特に大きな問題が見当たらなかった場合に通知されます。しかし、この「概ね妥当」という結果を得ることは、実は非常に難しいとされています。
経過観察
一部の点で改善が必要な問題が認められたものの、その内容が重大ではなく、今後の改善が期待できる場合にこの結果が伝えられます。この場合、改善報告書を提出した後、数ヶ月にわたって改善状況がチェックされ、もし改善が見られないと判断された場合は、翌年度に再度個別指導の対象となる可能性も考えられます。
再指導
複数の観点で問題が確認された場合や、比較的重大な問題が見つかった場合に「再指導」が通知されます。この結果を受けた歯科医院は、翌年度の個別指導の対象となる可能性が高く、状況によっては患者さんの診療内容をさらに詳しく調べる「患者調査」が行われた後に、改めて指導が実施されることもあります。
要監査
指導の過程で、監査が必要だと判断されるほどの不正や著しい不当行為が疑われた場合に「要監査」となります。通常、この状況に陥ると、個別指導は途中で中止され、直ちに本格的な「監査」へと移行するのが通例です。そのため、結果通知として後日「要監査」と伝えられることは稀で、大抵はその場で監査への切り替えが告げられることになります。
個別指導の対象となる歯科医院の選定理由

では、どのような歯科医院が個別指導の対象として選定されるのでしょうか。その理由や判断基準について見ていきましょう。
患者や元従業員からの情報提供
個別指導のきっかけとして、患者さんや過去にその歯科医院で働いていた元従業員からの情報提供が挙げられます。診療内容に疑問を抱いた患者さんからの連絡や、勤務中に不正な請求や不適切な医療行為を目撃した元従業員からの告発は、地方厚生局が個別指導の必要性を判断する上で重要な情報源となります。
これらの情報は、具体性が高く、信頼できると判断された場合に、優先的に調査の対象となることが多く、突然の個別指導通知につながるケースも少なくありません。日頃から患者さんへの丁寧な説明と、従業員との良好な関係構築を心がけることが、このようなリスクを未然に防ぐ上で重要と言えるでしょう。
過去の指導結果
過去に実施された指導の結果も、個別指導の対象となる重要な選定理由の一つです。例えば、集団的個別指導を受けた際に改善を促されたにもかかわらず、その後の状況で改善が見られなかったり、再び問題のある診療や請求が確認されたりした場合、地方厚生局はより詳細な確認が必要だと判断し、個別指導の対象とする可能性が高まります。
また、過去の個別指導で「再指導」とされた歯科医院は、その後の改善状況を確認するため、再度個別指導を受けることが一般的です。これは、過去の指導で指摘された問題点が本当に改善されたのかを確かめるためのフォローアップとして位置づけられます。
指導後の改善報告書の提出だけでなく、その後の診療内容や請求が継続的に適切に行われているかが評価されるポイントとなります。
高点数医療機関としての選定
レセプト1件あたりの平均点数が、都道府県の平均点数を大幅に超えている歯科医院は、「高点数医療機関」として個別指導の対象となることがあります。具体的には、前年のレセプト1件あたりの平均点数が都道府県平均の1.2倍を超え、かつ上位約8%に該当する歯科医院が集団的個別指導の対象となり、その結果によっては個別指導へ移行するケースが見られます。
重要なのは、単にレセプトの点数が高いというだけでなく、その点数の根拠となる診療内容が適正であるかが問われる点です。月のレセプト数が少ない医院の場合、必然的に平均点が高くなることがあり、何の不正がなくても指導対象になるケースも存在します。
高点数であることを理由に個別指導となった場合、診療内容と請求の妥当性を明確に説明できる準備が求められます。
監査での指摘事項
過去に実施された監査で、診療内容や診療報酬請求に関して何らかの指摘や注意を受けた歯科医院は、その後の状況を確認する目的で個別指導の対象となることがあります。監査は個別指導よりも厳格な調査であり、そこで不適切な点が認められたということは、継続的な改善が必要であると判断される要因となります。
監査で受けた指摘事項に対して、歯科医院がどのように改善策を講じ、実際にそれが実践されているのかを、個別指導の場で確認されることになります。監査の対象となった経験がある場合は、その後の保険診療全般において、より一層の注意と改善努力が求められると言えるでしょう。
新規個別指導後の状況
新しく開業した歯科医院が保険医療機関としての指定を受けた後に受ける「新規個別指導」の結果も、その後の個別指導の選定理由となり得ます。新規指導は教育的な意味合いが強いとされていますが、もしこの指導の場で、診療内容や請求に関して改善が必要だと判断されたり、不適切な点が指摘されたりした場合、改めて個別指導の対象とすることがあります。
これは、地方厚生局はその後の改善状況を継続的に確認するためです。新規開業の歯科医院は、指導を通して保険診療のルールへの理解を深めることが求められ、初期段階での適切な対応が、その後の個別指導の回避につながる重要なポイントとなるでしょう。
個別指導の対策とポイント

個別指導は、歯科医院にとって時に大きなプレッシャーとなるでしょう。しかし、適切な準備と心構えがあれば、この局面を乗り越えることは十分可能です。ここでは、個別指導に臨む上で特に意識すべき対策とポイントをまとめます。
通知到着後の冷静な対応
指導通知を受け取った際、まずは冷静に状況を把握することが何よりも大切です。慌てて対応を誤らないよう、通知の内容を隅々まで確認し、指導の対象期間や準備すべき書類、指導の目的などを正確に理解することから始めましょう。不安な気持ちになるのは当然ですが、焦らず、一つずつ段階を踏んで準備を進めることが重要です。
専門家との連携
歯科の個別指導に精通した弁護士やコンサルタントなど、専門知識を持つプロフェッショナルへの相談は非常に有効な手段です。彼らは、法的な観点や過去の事例に基づき、適切なアドバイスや書類作成のサポート、さらには指導当日の同席など、多岐にわたる支援を提供してくれます。
早期に専門家と連携することで、精神的な負担を軽減し、より戦略的な準備を進めることができるでしょう。自力で抱え込まず、頼れる専門家を見つけることが成功への第一歩となります。
徹底した書類準備
指導で最も重視されるのが、診療録やレセプト、エックス線写真、技工指示書といった客観的な証拠書類です。これらを指示された期間分、漏れなく、そして質問された際にすぐに提示できるよう、きちんと整理しておくことが求められます。
もし記録に不明瞭な点や不備が見つかった場合は、指導を受ける前に状況を整理し、論理的かつ合理的な説明ができるように準備しておくことが極めて重要です。記録はあなたの診療の根拠を示す唯一のものですから、その整合性は常に意識しておく必要があるでしょう。
指導日当日の誠実な姿勢
指導員からの質問に対しては、焦らず、常に冷静で誠実な態度で臨むことが大切です。事実に基づいて具体的に説明し、憶測や曖昧な返答は避けるようにしましょう。
質問の意図が不明な場合は、安易に答えるのではなく、「もう少し詳しく教えていただけますか」といった形で確認し、明確にしてから回答するよう心がけてください。また、質問されたこと以外に、自ら余計な情報を付け加えたり、関係のない話をしたりすることは控えるべきです。
情報が多すぎると、指導員が新たな疑問を抱くきっかけになる可能性もあります。
指導後の改善と再発防止
指導の結果通知を受け取ったら、指摘された問題点を真摯に受け止め、再発防止のための具体的な対策を講じることが肝要です。改善報告書は期限内に提出し、記載した改善策は実際に医院全体で徹底して実行に移しましょう。
スタッフへの指導や、保険診療のルールに関する定期的な勉強会の実施なども有効な手段です。これは、単に指導を乗り切るだけでなく、今後の医院経営の安定化と、より質の高い医療提供へとつながる大切なプロセスだと言えます。
まとめ
歯科医院にとって「指導」は、時に耳慣れない言葉かもしれませんが、これは保険診療の質を保ち、公正な医療提供を実現するために大切なプロセスです。集団指導から始まり、集団的個別指導、そして個別指導、新規指導と、その種類は多岐にわたります。特に個別指導は、患者さんの声や過去の状況、診療報酬の状況など、様々な要因から対象となる可能性があります。
しかし、恐れることはありません。通知が届いたら、まず冷静に状況を把握し、必要であれば専門家のサポートを求めること。そして、求められる書類をきちんと準備し、指導当日には誠実な姿勢で臨むこと。さらに、指導で得られた指摘を真摯に受け止め、改善と再発防止に努めること。
これらを着実に実践することで、個別指導は単なる試練ではなく、あなたの歯科医院がさらに成長し、地域医療に貢献していくための貴重な機会となるでしょう。このコラムが、皆さんの歯科医院運営の一助となれば幸いです。